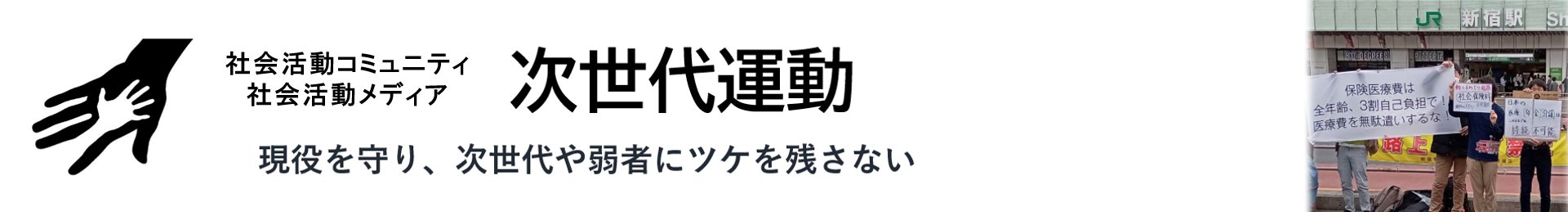2040年、圧倒的な税負担に苦しむ若者たちと、延命され続ける老人たち。過酷な徴税社会の中で、27歳のタカシは革命を決意する。政府の監視AI「カネミツ」によって思考すら管理される世界で、彼は仲間と共に「国立延命センター」の破壊を計画。しかし、元税務署員のオマロウが投げかける皮肉な現実が彼を揺さぶる。未来のために戦うのか、それとも支配を受け入れるのか――。近未来ディストピアを描く衝撃の社会派SF。
作:サトウヒロシ @satobtc
目次
第一章:徴税の日
2040年10月15日。東京の空はいつも通り、灰色に淀んでいた。雨が降るわけでもなく、ただ重たい雲が街を見下ろしている。俺の名はタカシ、27歳。かつては「未来を担う若者」と呼ばれた世代だが、今じゃ「税金の運搬機」と揶揄される存在だ。
朝6時。アパートの玄関に設置された徴税端末がけたたましく鳴り響く。画面には赤文字で「本日の納税額:38万4千円」と表示されている。給料の8割が消える瞬間だ。社会保険料60%、所得税80%、そして金融所得課税80%。貯蓄なんて夢物語で、銀行に預けたわずかな金さえも税務署の監視AI「カネミツ」に吸い取られる。昨日、バイト先で汗水垂らして稼いだ金は、今日には老人の医療費と年金に化ける。
「タカシ、払えよ。遅延ペナルティは1日3%だぞ」
端末から流れる無機質な合成音声が俺を急かす。仕方なく掌をスキャナーにかざすと、銀行口座から即座に金が引き落とされる。残高はマイナスに突入。借金生活の始まりだ。
街に出ると、いたるところで同じ光景が広がっている。コンビニの前では、スーツを着た中年男が「消費税40%だってさ…弁当一つで500円が消える」とぼやきながら袋を握り潰している。道端では年金受給者の集団がデモ行進中だ。「我々の命を奪うな! 若者はもっと働け!」と叫ぶ声が響くが、誰も耳を貸さない。俺たち若者は働きすぎて死にそうだってのに。
政府は言う。「少子高齢化は不可逆だ。社会保障費が予算の90%を超えた今、税収を増やす以外に道はない」と。確かに老人は増えた。平均寿命は95歳を超え、街は車椅子と介護ロボットで溢れている。でも、その「命を支えるコスト」は俺たちの首を絞める鎖だ。相続税80%のおかげで、親が死んでも遺産は国に没収。家一軒残すことすら許されない。
夜、俺は仲間と薄暗い地下バーに集まる。ここは「非課税ゾーン」と呼ばれる闇市場だ。政府の監視が届かない数少ない場所。酒は密造だし、煙草は密輸品。だが、それでも俺たちは笑う。笑うしかねえんだ。
「なぁ、タカシ。革命でも起こすか?」隣に座るユウキが冗談めかして言う。彼の目は血走り、手は震えている。過労と貧困で半狂乱だ。
「革命ねぇ…税務署のAIが俺たちの脳みそまで徴収しちまうぜ」と俺は返す。笑い声が響くが、それは空虚で、すぐに消える。
その夜、俺は夢を見た。税金の数字が空を埋め尽くし、俺を押し潰す夢だ。目覚めた時、枕は汗でびしょ濡れだった。そしてまた、朝6時。徴税端末が鳴り響く。
この世界に希望はない。ただ、納税と老人の延命が永遠に続くだけだ。
第二章:延命の工場
翌日、俺はバイト先の配送業務で「国立延命センター」へ向かった。政府が誇る「高齢者保護の聖地」。トラックに積まれたのは医療物資だ。人工栄養剤、酸素タンク、薬剤の入ったカプセル。どれも老人の命を無理やり繋ぎ止めるための道具だ。
センターに着くと、白衣を着た職員が無言で荷物を検品する。俺は荷台から段ボールを下ろしながら、施設の奥を覗き見た。そこには信じられない光景が広がっていた。
巨大なホールに、無数の老人たちが横たわっている。いや、「横たわる」というより、機械に固定されていると言ったほうが正しい。頭から足までチューブに繋がれ、人工呼吸器の規則的な音が響き渡る。彼らの目は虚ろで、半分開いた口からは涎が垂れている。まるで生きている死体だ。職員の一人が俺に近づいてきて、淡々と説明を始めた。
「ここでは一人あたり月100万円かけて延命してる。栄養剤が30万、薬剤が20万、機械の維持費と人件費で50万だ。国の予算の半分以上がこういう施設に消えてるよ」
「100万…」俺は思わず呟いた。「それで何人いるんだ?」
「このセンターだけで1万人。全国だと500万人以上だな。平均寿命が100歳を超えた今、こいつらを切り捨てるわけにはいかない。法律で決まってるからな」
老人たちの体に刺さったチューブは、まるで寄生虫のようだった。血や液体が流れ込むたび、彼らの胸がわずかに上下する。でも、あれは生きているって言えるのか? 俺の給料の8割がこんな場所に流れ込んでると思うと、吐き気がした。
帰り道、トラックのラジオから政府のプロパガンダが流れてきた。
「我々は全ての命を尊ぶ社会を築きました。高齢者の皆様に安心を。若者に感謝を。」
感謝? 冗談じゃない。俺たちの血と汗が、チューブの中で腐っていく老人たちに注ぎ込まれてるだけだ。
その夜、地下バーでユウキと再会した。彼はいつになく真剣な顔で俺に囁いた。
「タカシ、俺、決めたよ。こいつらをぶっ壊す。延命センターを止めるんだ」
「どうやってだよ?」俺は半笑いで返した。だが、ユウキの目は本気だった。
「爆弾だよ。仲間が集まってる。俺たちゃ税金の奴隷じゃない。生きる権利を取り戻すんだ」
俺は言葉を失った。革命だって? 確かに、この社会は腐ってる。老人を延命する機械に縛られ、若者は貧困と過労で死に絶える。でも、爆弾なんて…無茶だろ。
「考えさせてくれ」俺はそう言って席を立った。
家に帰ると、また徴税端末が鳴り響く。「追加納税:5万円。延命センター運営費増額分」と表示されている。俺は拳を握り潰しそうになった。頭の中で、チューブに繋がれた老人たちの顔と、ユウキの血走った目が交錯する。
このままじゃ終われない。そんな思いが、俺の中で初めて芽生えた。
第三章:監視の網
翌朝、俺はユウキの提案が頭から離れなかった。爆弾。革命。現実味がないように思えたが、徴税端末の無機質な音が鳴るたび、その考えが現実の重みを帯びていく。俺は決めた。ユウキに会って、詳しい話を聞く。
地下バーに着くと、ユウキはすでに数人の仲間とテーブルを囲んでいた。薄汚れた作業着を着た男たちと、疲れ切った目をした女たち。年齢は20代から30代前半。俺と同じ、税金の奴隷だ。ユウキが俺を見て立ち上がり、肩を叩いた。
「来てくれたか、タカシ。こいつらが俺たちの仲間だ。紹介するよ」
一人が名乗った。「アキラだ。元エンジニア。延命センターの機械を設計してたことがある」
「設計?」俺は驚いて聞き返した。
「ああ。だが、俺が作ったのは命を救う機械だったはずだ。今は…ただのゾンビ製造機だよ。あんなものに税金が消えるなんて我慢ならねえ」アキラの声は怒りに震えていた。
ユウキが地図を広げた。国立延命センターの設計図だ。
「ここが電源施設。ここを爆破すれば、センター全体が止まる。老人たちは死ぬだろうが、正直、それが国のためだ。俺たちの未来のためだ」
「待てよ」と俺は遮った。「そんなことしたら、政府が黙っちゃいない。すぐ捕まるぞ」
ユウキがニヤリと笑う。「だからこそ、準備がいる。タカシ、お前は配送員だろ? センターに出入りできる。内部の情報を頼む」
その瞬間、背筋が冷えた。俺のスマホが振動したんだ。画面を見ると、税務署AI「カネミツ」からの通知。
「警告:反政府的会話が検知されました。直ちに活動を中止し、税務署に出頭せよ。出頭期限:24時間以内」
「やべえ!」ユウキが叫び、地図を畳んだ。「どうやってバレたんだ?」
アキラが歯を食いしばる。「監視網だよ。スマホ、街のカメラ、全部カネミツに繋がってる。俺たちの声も盗聴されてたんだ」
バーから逃げ出す間際、俺は気づいた。政府は俺たちを完全に掌握してる。税金を取るだけじゃない。思考すら監視されてるんだ。ユウキが俺の手を掴み、裏口へ走りながら言った。
「タカシ、もう後戻りできねえぞ。一緒に戦うか、奴隷のまま死ぬかだ」
夜の路地を走りながら、俺は延命センターの光景を思い出した。チューブに繋がれた老人たち。あれは生きてる人間じゃない。ただ、政府が「命を尊ぶ」と言い訳するための道具だ。月100万円かけて延命される彼らのために、俺たちは生き地獄を強いられてる。
「やるよ」俺はユウキに言った。「俺も戦う」
その夜、俺たちはアジトに身を潜めた。古い倉庫の地下だ。アキラが持ち込んだ設計図と爆薬の材料を前に、計画が具体化し始めた。だが、カネミツの警告が頭を離れない。24時間後、俺たちが捕まるか、それとも一撃を食らわせられるか。時間との勝負が始まった。
翌朝、俺は配送員のふりで延命センターに戻った。荷物を運びながら、電源施設の位置を確認する。職員の目をかいくぐり、カメラの死角を探す。心臓がバクバクしてる。だが、俺の中で何かが変わった。この社会をぶち壊すためなら、俺の命だって賭けられる。そんな覚悟が初めて生まれたんだ。
第四章:オマロウの説教
倉庫の地下アジトで、俺たちは爆破計画を詰めていた。アキラが電源施設の配線図を指差し、ユウキが爆薬のタイマー設定を説明する。緊張感が空気を重くしていたその時、扉が軋む音が響いた。俺たちは一斉に立ち上がり、ナイフや鉄パイプを手に持つ。敵か? カネミツの追跡がもう来たのか?
だが、入ってきたのは見知らぬ男だった。50代くらい、薄汚れたコートを羽織り、白髪交じりの髪を無造作に掻き上げている。手に持った酒瓶が揺れ、アルコールの匂いが漂ってきた。ユウキが叫んだ。
「誰だ、お前! どうやってここを見つけた?」
男はニヤリと笑い、低い声で答えた。
「オマロウって呼べ。元税務署の下っ端だよ。お前らの噂を聞きつけてな、興味が湧いたんだ」
「噂?」俺は眉をひそめた。「カネミツに通報する気か?」
オマロウは手を振って笑いものにした。「まさか。あのAI野郎にはうんざりだ。俺はただ、お前らに忠告しに来ただけさ。お前らもいつかは老人になるんだぜ?」
その言葉に、俺たちは顔を見合わせた。ユウキが一歩前に出て、怒鳴った。
「ふざけんな! 俺たちが老人になる前に、この社会に殺されるんだよ!」
オマロウは酒を一口飲んで、テーブルにドカッと座った。
「まあ、落ち着けよ。今はお前らが搾り取られてる側だ。社会保険料60%、所得税80%、確かにキツイさ。でもな、考えてみろ。平均寿命95歳だ。今27歳のお前があと68年生きりゃ、延命センターでチューブに繋がれて月100万もらえる側になる。徴税されてるのは、未来の自分への投資だと思えばいいじゃねえか」
「投資?」アキラが吐き捨てるように言った。「俺たちが死に物狂いで働いて、老人がゾンビみたいに生き続けるのが投資かよ? そのシステムが俺たちを潰してるんだ!」
オマロウは肩をすくめた。「そうやって若者はいつも文句を言う。だがな、歴史を見てみろ。どの時代も若者が老人を支えてきた。今は極端なだけだ。お前らが老人になった時、若い連中に同じこと言われるぜ。『お前らの延命のために税金払え』ってな。お前らもいつかは老人になるんだからさ」
その言葉が、俺の胸に刺さった。確かに、俺だって年を取る。でも、この社会じゃ老人になる前に死ぬか、精神が壊れるかのどっちかだ。ユウキがオマロウを睨みつけて言った。
「だったら何だよ? このまま奴隷みたいに耐えろってか? ふざけるな。俺たちは未来を取り戻すんだ!」
オマロウは立ち上がり、コートのポケットから何かを取り出した。小さなUSBメモリだ。
「まあ、そう熱くなるな。お前らの気持ちは分かるよ。これをやろう。延命センターのセキュリティコードだ。昔、税務署で盗んだデータさ。使い方はお前ら次第だ。俺はもう疲れたよ。この腐った世界に付き合うのはな」
俺はUSBを受け取った。オマロウの目には、諦めと僅かな期待が混じっていた。彼は本当にただの酔っ払いなのか、それとも何か企んでるのか? ユウキが俺に囁いた。
「信用できるか分からねえが、このコードがあれば計画が早まる。タカシ、どうする?」
俺はUSBを握り潰しそうなくらい力を込めた。「やるしかないだろ。オマロウが何を考えてるかは知らねえ。でも、俺たちはもう引き返せない」
オマロウは酒瓶を手に、ふらりとアジトを出て行った。去り際にまた呟いた。「お前らもいつかは老人になるんだぜ…」その声は、暗闇に溶けるように消えた。
その夜、俺たちはセキュリティコードを解析し始めた。アキラが言うには、これで延命センターの電源施設に直接アクセスできる可能性がある。計画は一気に現実味を帯びてきた。でも、オマロウの言葉が頭から離れない。俺たちが老人になった時、この戦いは無意味だったと思える日が来るのか? いや、そんな未来が来る前に、俺たちはこの社会を変えるんだ。
第五章:崩壊の火種
計画の実行日は翌日に決まった。俺、ユウキ、アキラ、そして数人の仲間は、夜明け前にアジトを出発した。オマロウが残したUSBのセキュリティコードを使えば、延命センターの電源施設に侵入し、爆薬を仕掛けることができる。アキラがノートパソコンでコードを解析し、ユウキが爆薬のタイマーを調整する。俺は配送トラックを運転しながら、センターへの潜入ルートを確認する役割だ。
夜の街は静かだったが、監視カメラの赤い光が至るところで点滅している。カネミツの目だ。俺たちはフードを深く被り、カメラの死角を縫うように進んだ。センターに近づくにつれ、心臓の鼓動が耳に響く。失敗すれば終わりだ。捕まるか、殺されるか。でも、このまま奴隷の人生を続けるよりはマシだ。
センターの裏口に着くと、アキラがUSBを端末に差し込んだ。画面に緑の文字が流れ、数秒後、「アクセス許可」の表示が点灯する。俺たちは息を殺して中へ滑り込んだ。電源施設は地下にあり、無数のケーブルと機械がうなり声を上げていた。チューブに繋がれた老人たちの命を支える心臓部だ。一人あたり月100万円。全国で200万人以上。その金は俺たちの血と汗から搾り取られたものだ。
ユウキが爆薬を設置し始めた。タイマーは10分に設定。爆破後、俺たちは逃げ切れるかどうかの賭けだ。作業中、頭にオマロウの声が響いた。「お前らもいつかは老人になるんだぜ」。確かに、そうかもしれない。でも、その未来が来る前に、俺たちは生きる権利を奪われてる。このシステムを壊さなきゃ、何も始まらない。
「準備できた!」ユウキが叫び、俺たちは出口へ走った。だがその瞬間、警報が鳴り響いた。赤いランプが点滅し、スピーカーからカネミツの合成音声が流れる。
「反政府活動を確認。直ちに投降せよ。抵抗した場合、即時処罰を執行する」
「クソッ、バレたのか!」アキラが叫び、パソコンを叩く。「セキュリティコードが古かったのか…カネミツに上書きされてたんだ!」
逃げる間もなく、武装した警備ドローンが通路を塞いだ。赤外線センサーで俺たちを捕捉し、警告音が鳴り続ける。ユウキがナイフを手に持つが、そんなものでどうにかなる相手じゃない。絶体絶命だと思った瞬間、爆発音が響いた。タイマーが作動したんだ。電源施設が炎に包まれ、電気が一瞬にして落ちる。ドローンの動きが止まり、俺たちは暗闇の中を走った。
外に出ると、センター全体が停電していた。遠くで火の手が上がり、職員たちが慌てて叫び合う声が聞こえる。チューブに繋がれた老人たちの命は、今この瞬間、消えつつある。俺の胸に罪悪感がチクリと刺さったが、すぐにそれを振り払った。あれは生きてる人間じゃない。政府の言い訳だ。
だが、喜ぶ暇はなかった。街中にサイレンが鳴り響き、ヘリコプターの灯光が俺たちを照らし始めた。カネミツの追跡は終わらない。ユウキが息を切らしながら言った。
「タカシ、分散しろ! また会おうぜ!」
俺たちは別々の路地に逃げ込んだ。背後で銃声が響き、心臓が縮み上がる。仲間がやられたのか? 分からない。でも、立ち止まるわけにはいかない。
夜が明ける頃、俺は廃ビルに身を隠した。息を整えながら、スマホを取り出す。ニュース速報が流れていた。
「国立延命センターで爆破テロ。5000人以上の高齢者が死亡。政府は非常事態を宣言し、犯人グループの即時逮捕を表明」
画面には、炎上するセンターの映像と、泣き叫ぶ職員の姿。政府の報道官が冷静な声で続ける。
「我々は命を尊ぶ社会を維持してきた。若者への負担は理解するが、このような暴力は許されない。犯人は必ず裁かれる」
俺はスマホを握り潰しそうになった。あいつらが命を尊ぶ? ふざけるな。俺たちを奴隷にして、老人をゾンビに変えたのは誰だよ。だが、同時にオマロウの言葉がまた浮かんだ。「お前らもいつかは老人になる」。その時が来たら、俺はこの選択を後悔するのか? いや、そんな未来はもう来ない。この社会が続く限り、俺たちに未来はないんだ。
外で足音が近づいてきた。カネミツの追跡隊だ。俺は立ち上がり、ビルを抜け出す。戦いはまだ終わらない。ユウキやアキラが生きてるなら、また合流して次の一手を考える。俺たちは負けない。この腐った世界を変えるまで。
第六章:追跡の影
廃ビルの裏口から脱出した俺は、息を殺して路地を走った。朝焼けが空を染める中、遠くでヘリコプターのローター音が響き、ドローンのサーチライトが地面を這う。カネミツの追跡網は容赦ない。俺の足音すら拾われて、位置を特定されるかもしれない。ポケットのスマホは電源を切ったが、それでも監視の目を逃れるのは難しい。
ユウキやアキラとはぐれてから数時間。仲間が生きてるのか、捕まったのか、それとも死んだのか、分からない。胸が締め付けられるが、今は考える時間もない。延命センターの爆破は成功した。5000人以上の老人が死に、政府は非常事態を宣言した。でも、俺たちの戦いはまだ始まったばかりだ。
路地の奥で蹲り、物陰に隠れる。すると、近くの電光掲示板が点灯し、カネミツの声が流れてきた。
「市民各位。反政府テロリストが逃亡中です。以下の顔写真を確認し、発見次第通報してください。報奨金:1人につき500万円」
画面に映し出されたのは、俺、ユウキ、アキラの顔だった。監視カメラの映像を基にした鮮明な画像だ。俺の胃がキリキリした。500万円。貧困に喘ぐ市民なら、誰だって俺たちを売るだろう。この社会は金で簡単に裏切る。
——————————————————————————————————
一方、東京の政府庁舎では、非常事態対策室が慌ただしく動いていた。中央のモニターには、延命センターの焼け跡と、タカシたちの顔写真が映し出されている。対策室長の山田は、眉間に深い皱を寄せながら、カネミツAIの報告を聞いていた。
「犯人グループの位置は特定中です。逃亡ルートの予測精度は87%。ドローン部隊と地上部隊を配置済みです」カネミツの声は冷たく、感情がない。
山田は苛立たしげに机を叩いた。「87%じゃ足りん! こいつらが逃げ切ったら、他の若者どもが真似するぞ。延命システムが崩壊すれば、この国は終わりだ!」
隣に立つ副官が口を開く。「しかし、室長。国民の不満は限界に達しています。社会保障費が予算の90%を超え、税率は史上最高。若者の暴発は予測できたはずです」
「黙れ!」山田が怒鳴った。「若者が何だ。奴らは働いて税を払うのが役目だ。老人を支えるのが国の基盤なんだよ。あいつらが命の価値を分かってないだけだ」
モニターに新たな映像が映し出された。焼け落ちた延命センターの内部。チューブが切断され、横たわる老人たちの遺体が映る。一人あたり月100万円かけて延命されていた命が、一瞬で消えた。山田は目を細め、呟いた。
「こいつらは怪物だ。だが、見せしめにする。国民に分からせるんだ。抵抗すればこうなるとな」
カネミツが補足する。「提案:犯人逮捕後、公衆処刑をライブ配信。視聴率予測:92%。国民への抑止効果は最大化されます」
山田は頷いた。「許可する。すぐ準備しろ」
——————————————————————————————————-
俺は路地を抜け、古い下水道に身を潜めた。臭気が鼻をつくが、ここならドローンのセンサーも届きにくい。しばらくして、聞き慣れた足音が近づいてきた。ユウキだ。顔は泥だらけで、肩に血が滲んでいる。
「タカシ、無事か!」彼は息を切らしながら俺に近づいた。
「お前こそ大丈夫か? アキラは?」
「分からない。爆破後にドローンに追われて…俺はなんとか逃げた。アキラも生きてりゃいいが」
俺たちは互いに肩を叩き、生きてることを確認した。だが、安心してる暇はない。ユウキがポケットから小さなラジオを取り出し、電源を入れる。政府の声明が流れていた。
「テロリストの公衆処刑を予定。国民は協力し、犯人を速やかに通報せよ」
ユウキが歯を食いしばる。「見せしめかよ。俺たちを殺して、若者を黙らせようって魂胆だ」
俺は拳を握った。「だったら、もっとでかい一撃を食らわせるしかない。次はどこを狙う?」
ユウキが目を光らせて言った。「カネミツの中枢だ。あのAIを潰せば、監視網も徴税システムも止まる。俺たちの勝ちだ」
その時、下水道の入り口で金属音が響いた。ドローンが近づいてくる。俺とユウキは顔を見合わせ、暗闇の奥へ走った。カネミツを潰す。それが次の目標だ。でも、オマロウの声がまた頭に響く。「お前らもいつかは老人になる」。その言葉を振り払うように、俺は走り続けた。この社会が変わるなら、どんな代償だって払う。
第七章:再会と決意
下水道の暗闇を抜け、俺とユウキは古い工場跡にたどり着いた。錆びた鉄骨と崩れたコンクリートの隙間に身を隠し、ようやく一息つけた。ユウキが肩の傷を手当てしながら言った。
「カネミツの中枢は東京タワー跡地の地下にある。あそこがAIのサーバーファームだ。監視網も徴税システムも全てそこから制御されてる」
「セキュリティはどうだ?」俺は尋ねた。
「最悪だよ。ドローン、武装警備員、生体認証のゲート。だが、アキラが生きてりゃ突破できる。あいつなら内部の構造を知ってるはずだ」
その時、工場の奥から足音が聞こえた。俺たちは息を殺し、鉄パイプを握る。敵か? だが、暗闇から現れたのはアキラだった。服はボロボロで、顔には殴られた跡がある。ユウキが駆け寄り、彼の肩を掴んだ。
「お前、生きてたのか!」
アキラは苦笑いを浮かべた。「ギリギリだよ。ドローンに追われて、捕まりかけた。だが、運良く下水道に逃げ込んでな…お前らに会うまで隠れてた」
「怪我は?」俺が聞くと、アキラは首を振った。
「大丈夫だ。それより、延命センターの爆破で政府が本気で動いてる。カネミツが俺たちのデータを全国に流して、通報を呼びかけてる」
アキラがポケットから取り出したのは、小さなデータチップだった。「これ、延命センターから盗んだバックアップデータだ。カネミツのセキュリティコードが一部入ってる。これがあれば、中枢に侵入するチャンスがある」
ユウキが目を輝かせた。「お前、やるじゃねえか! これでカネミツをぶっ潰せる!」
俺は頷いた。「なら、すぐ計画を立てる。時間がない」
——————————————————————————————————-
その夜、俺たちは工場跡で作戦を練った。アキラがデータチップを解析し、カネミツ中枢の入り口とサーバールームの位置を特定。ユウキが爆薬の残りを確認し、俺が潜入ルートを提案した。東京タワー跡地は政府の重要施設で、普段は市民の立ち入りが禁止されている。だが、俺の配送員の身分証を使えば、物資搬入のふりで近づけるかもしれない。
「問題は警備だ」アキラが言った。「生体認証を突破するには、内部の誰かを味方に付けるか、システムをハックする必要がある。俺の知識じゃ限界がある」
ユウキがニヤリと笑う。「なら、オマロウを引っ張り込むか? あいつ、元税務署員だろ。内部の仕組みを知ってるはずだ」
俺は一瞬考え込んだ。オマロウ。あの酔っ払いの言葉がまた浮かぶ。「お前らもいつかは老人になる」。だが、彼のくれたセキュリティコードは確かに役立った。信用できるかは分からないが、今は賭けるしかない。
「探しに行く。オマロウなら地下バーにいるかもしれない」
翌朝、俺は単独で地下バーへ向かった。街は戒厳令下で、市民の目が鋭く俺を追う。報奨金目当ての通報者がどこに潜んでるか分からない。バーに着くと、オマロウはいつものように酒瓶を手に、カウンターに突っ伏していた。
「オマロウ、起きろ。頼みがある」俺が肩を叩くと、彼は眠そうな目で俺を見上げた。
「お前か…ニュースで見たぜ。延命センターをぶっ壊した英雄さんだな。お前らもいつかは老人になるって言ったのに、無駄な抵抗だよ」
「黙れ」と俺は遮った。「カネミツを潰す。協力しろ。お前なら中枢のセキュリティを知ってるだろ」
オマロウはしばらく俺を睨み、やがて笑い出した。「面白い。お前ら、どこまで本気だ? いいよ、付き合ってやる。ただし、俺が生き残れる保証が欲しいね」
「約束する。成功したら、新しい社会でお前にも居場所を作る」
——————————————————————————————————-
数時間後、俺たちは東京タワー跡地に集結した。アキラがデータチップでゲートのロックを解除し、オマロウが内部の警備員の動きを予測。俺とユウキは爆薬を抱え、地下への階段を降りる。サーバーファームは冷たく静かで、無数の光が点滅していた。カネミツの中枢だ。ここを壊せば、監視も徴税も止まる。
だが、サーバールームに足を踏み入れた瞬間、スピーカーから声が響いた。
「侵入者確認。防衛システム起動。投降しない場合、即時排除します」
カネミツの声だ。天井から武装ドローンが降りてきて、赤いレーザーが俺たちを狙う。オマロウが叫んだ。
「やっぱり裏切られると思ったぜ! お前ら、俺を盾にしろ!」
ユウキが爆薬を手に叫ぶ。「タカシ、時間稼ぎしてくれ! 俺が仕掛ける!」
俺は鉄パイプを手にドローンに向かって走った。戦いが始まった。この一撃で全てが変わる。俺たちの未来を賭けた最後の賭けだ。
第八章:終焉の光
サーバールームに響くドローンの機械音と銃声が、俺の耳を劈く。俺は鉄パイプを手に、飛来するドローンに飛びかかった。一台を叩き落とすと火花が散り、床に墜落する。だが、次々と新たなドローンが湧いてくる。カネミツの防衛システムは俺たちを容赦なく排除しようとしていた。
ユウキは爆薬を抱え、サーバーの基幹部へ走る。アキラがデータチップを差し込んだ端末を操作し、ドローンの制御を妨害しようと試みる。オマロウは壁に身を隠し、酒瓶を手に震えていた。
「タカシ、時間稼ぎしろ! あと5分だ!」ユウキが叫ぶ。タイマーをセットし、爆薬をサーバーのコアに固定する。5分。それが俺たちの未来を決める時間だ。
ドローンのレーザーが俺の腕をかすめ、血が滴る。痛みで視界が揺れるが、立ち止まるわけにはいかない。鉄パイプを振り回し、もう一台を破壊する。アキラが叫んだ。
「ドローンの制御を一部ジャックできた! 動きが鈍るはずだ!」
その言葉通り、ドローンの動きが一瞬遅くなった。俺は隙をついてユウキの側へ駆け寄る。タイマーは残り3分を示していた。
だが、その時、カネミツの声が再び響いた。
「無駄な抵抗です。貴様らの行動は全て記録済み。サーバーが破壊されても、バックアップが全国に存在します。この社会は揺るぎません」
ユウキが歯を食いしばる。「嘘だろ…バックアップだと?」
アキラが顔を青ざめさせた。「本当かもしれない。カネミツは分散型システムだ。ここのサーバーを潰しても、完全には止まらない可能性が…」
絶望が俺たちを包みかけた瞬間、オマロウが立ち上がった。酒瓶を手に、ふらつきながらサーバーへ近づく。
「お前らもいつかは老人になるって言ったよな。でも、俺はもう待てねえ。この腐った世界に付き合うのは終わりだ」
彼は酒瓶を振り上げ、サーバーの冷却装置に叩きつけた。ガラスが砕け、液体が飛び散る。次の瞬間、冷却装置から火花が上がり、爆音と共に煙が立ち上った。
「オマロウ、何!?」俺が叫ぶと、彼は笑った。
「素人なりの一撃さ。バックアップがあっても、こいつが過熱すればしばらく機能しねえよ。逃げろ、タカシ!」
タイマーが残り1分を切った。俺たちはオマロウを置いて走った。彼の犠牲が無駄にならないよう、生き延びて次を考えるしかない。出口へ向かう途中、背後で爆発音が響き、サーバールームが炎に包まれた。カネミツの声が途切れ、ドローンの動きが完全に停止する。成功したんだ。
終章:お前もいつか老人になる
爆破から数時間後、俺とユウキ、アキラは郊外の森に逃げ込んだ。遠くで東京の街が騒然としているのが見える。ニュース速報が流れる小さなラジオを手に、俺たちは耳を傾けた。
「カネミツ中枢が攻撃を受け、システムが一時停止。徴税および監視網が全国で機能不全に。政府は混乱を収拾中ですが、市民の一部が反乱を始めています」
ユウキが拳を握った。「やったぜ…俺たちの勝ちだ!」
アキラが冷静に言う。「まだだ。バックアップがあるなら、カネミツは復旧する。だが、この混乱はチャンスだ。若者たちが立ち上がれば、社会を変えられるかもしれない」
俺は森の奥を見ながら考えた。オマロウの最後の言葉。「お前らもいつかは老人になる」。彼はそれを信じてたかもしれない。でも、俺たちはその未来を待つのじゃなく、今を変えるために戦った。延命センターの老人たちは死に、カネミツは止まった。社会保障費に縛られたこのディストピアは、崩れ始めている。
その日から、街では若者たちのデモが広がった。徴税端末を壊し、政府庁舎に火を放つ者も現れた。政府は必死に秩序を取り戻そうとしたが、カネミツの復旧は遅れ、混乱は収まらない。俺たちは森に潜み、次の行動を計画した。もう奴隷じゃない。俺たちは新しい未来を作る。
数日後、ラジオから新たな声が流れた。市民が結成した「自由連合」のリーダーを名乗る若者だ。
「俺たちは税金の奴隷じゃない。命を尊ぶ社会を言うなら、若者も老人も共に生きられる世界を作ろう。戦いはこれからだ」
俺はユウキとアキラを見た。「行くか?」
二人が頷く。俺たちは立ち上がり、森を出た。戦いは終わらない。でも、初めて希望が見えたんだ。
エピローグ:新しい天秤
2045年、春。東京の街はかつての灰色の静寂を脱し、雑多な喧騒に包まれていた。カネミツの中枢が破壊されてから5年。俺、タカシは32歳になった。あの戦いの日から、俺たちの人生は大きく変わった。
カネミツの停止は、政府の徴税システムと監視網を一時的に崩壊させた。若者たちの反乱は全国に広がり、「自由連合」が各地で結成された。税率は引き下げられ、社会保障費は予算の90%から60%まで縮小。延命センターは次々と閉鎖され、チューブに繋がれた老人たちは自然に命を終えた。月100万円の延命費用は、若者への教育や雇用の支援に回されるようになった。
でも、全てが理想通りにはいかなかった。政府はバックアップシステムでカネミツを部分的に復旧させ、秩序を取り戻そうとした。自由連合と政府の間で小競り合いが続き、犠牲者も出た。それでも、俺たちが起こした波は止まらなかった。街には、新しい社会を求める声が響き続けている。
俺は今、ユウキとアキラと共に小さなコミュニティを運営してる。東京郊外の廃墟を再利用した場所で、若者たちが集まり、互いを支えながら暮らす。ユウキは怪我が癒えた後、連合のリーダーとして各地を飛び回ってる。アキラは技術者として、監視システムに頼らない新しい通信網を構築中だ。俺は物資の調達と若者たちの指導を担当してる。戦いの日々から、少しだけ穏やかな時間を取り戻した。
ある日、コミュニティの広場で、ユウキが戻ってきた。彼は疲れた顔で笑いながら言った。
「タカシ、見たか? 政府が新しい法案を通したぜ。所得税は最高50%、社会保険料は40%まで下がった。俺たちの勝ちだよ」
「完全じゃないけどな」俺は返す。「まだ老人を支える負担はある。でも、昔みたいに若者が潰されることはない」
アキラが横から口を挟む。「カネミツの監視網も弱体化した。俺の通信網が完成すれば、市民が自由に声を上げられる。もう奴隷の時代は終わりだ」
その夜、俺たちは焚き火を囲んで酒を飲んだ。かつての地下バーの仲間たちも集まり、笑い声が響く。ふと、オマロウの顔が浮かんだ。あの酔っ払いは最後に俺たちを救って死んだ。「お前らもいつかは老人になる」。その言葉が、今は少し違って聞こえる。確かに俺たちは年を取る。でも、その時が来ても、この社会なら生きていけるかもしれない。
焚き火の向こうで、若い子たちが未来の話をしているのが聞こえた。
「俺、医者になって、老人も若者も助けたい」
「私は農業やりたい。食料を自給できれば、税金に頼らなくて済むよ」
彼らの目は、俺たちがかつて失っていた希望で輝いている。俺は空を見上げた。灰色の雲は薄れ、星がちらりと覗いていた。
戦いは完全には終わらない。政府との軋轢も、経済の不安定さも残ってる。でも、俺たちが壊した天秤は、新しい形で再構築されつつある。若者と老人が共に生きられる世界。それはまだ遠い夢かもしれないが、俺たちの手でその第一歩を踏み出したんだ。
「タカシ、乾杯しようぜ」ユウキが杯を掲げる。
「未来のために」アキラが続く。
俺は笑って杯を合わせた。「ああ、未来のために」
風が吹き、焚き火の炎が揺れた。新しい天秤が、この世界を少しずつ変えていく。その重さを、俺たちはこれからも背負い続けるだろう。